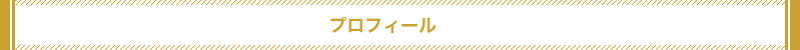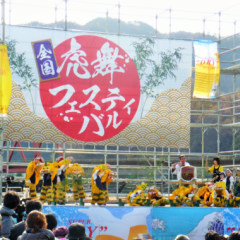【震災から3年】いつまでも忘れない ~いま大切なのは、つづける“わ” Vol.9~ 『芸能は、人を、土地を生かすことができるのか』
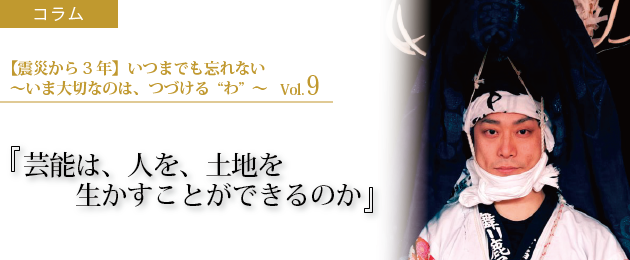
小岩 秀太郎
東北地方は「郷土芸能の宝庫」である。
東日本大震災被災地の復興を支えたのは、これら郷土芸能や祭りであった。携わる人たちや道具の多くを津波や火災で失くしながらも、次々と復活を果たしていく姿が励みとなり、希望となり、話題になった。
また「何としても続けなければならない」と伝承者たちは口々に語るのである。芸能や祭りがその土地を土地たらしめるための核であったからに他ならず、例えば地域の人が亡くなった際の鎮魂供養を芸能が担ってきたという事実は、震災のような災害があろうとなかろうと長く続いてきた慣習であり、日常の風景であったのだ。全てが無になったかのような世界を目の前にして、彼らが取り戻そうとした日常の一風景に、芸能が在るのは当たり前のことだっただろう。
芸能・祭りの支援とは
被災地における郷土芸能や祭りの役割が認識されるようになり、これらに対する全国、多方面からさまざまな支援が行われるようになった。
芸能や祭りを支援する、ということは一体どういうことだったのだろう。発災から4年を前に改めて見つめ直してみると、金銭をはじめ経済的な支援によって、岩手県や宮城県で被災した芸能の半分以上が復活、あるいは復活の目途が立ち、活動を再開させている(無形文化遺産情報ネットワーク http://mukei311.tobunken.go.jp/参照)。太鼓や笛といった楽器にはじまり、装束や獅子頭、そして山車や神輿といった大型で高価なものまでが1~2年で揃い、震災前と同じように、あるいは震災前よりも盛んに祭りが執り行われるようになった地域もある。震災前まで過疎・少子高齢化で中断目前だったり数十年も休止していた芸能が復活した例も少なくはない。
このような復活劇は、震災前までの芸能や祭りに対する支援体制では、到底なし得なかったものではないだろうか。
実は、震災前までは主に自治体の教育委員会が「文化財」としてわずかな補助金、助成金を、「文化財」として保存・保護すべき対象と指定された芸能や祭りに対してのみ配分する、という例が多く、極端に言えば「文化財」に指定されていない、認識されていない芸能は、自ら活動費を作っていくほかなかったのである。特に東日本大震災被災地の芸能や祭りに限って、こうした「文化財」に指定されていない団体が非常に多かったため、調査も十分でなく、震災直後に支援をするために実態を把握するのがとても難しかった。
把握できたとて、支援の頼みの綱は教育委員会ばかりか、と心もとない気持ちでいたところ、企業メセナ協議会の「GBFund:芸術・文化による復興支援ファンド」のような「文化財指定」の枠ではない視点から芸能や祭りを支援できるシステムが各方面から立ち上がり、上記のように迅速で、目に見える形での成果を得、かつ、芸能や祭りが被災地復興には不可欠であるとのインパクトを世の中に発信できたのであった。
しかし一方で、芸能が地域の芸能として生きていく運命にある以上、地域の人々がその復活に力や知恵を尽くしていくのが大前提である。いつまでも外部からの経済的・物的支援に頼り続けることはできない。
震災直後の緊急時の中で、モノが無いなりにやり繰りをして再開に向かっていった姿や、それまで一緒にやることのなかった芸能同士が道具の貸し借りをするといった新たな交流の形が出来たり、震災前までは豊作や大漁祈願を担っていた芸能が鎮魂という新しい意味を持つようになった事実に、私たちは触れた。
その時々の必要性や暮らしぶりにあわせて知恵を出し合い、姿を柔軟に変えていく人々と芸能。自分たちで作り上げていくからこそ、それらは意味を持ち、活き活きと輝いた姿を見せるようになる。「保護」「保存」「形を変えず正式に」という義務感がいつの間にか芸能を縛り付けていたのかもしれない。そのことがそのまま、芸能から、人から、活力を奪い、土地力の弱体化につながっていったともいえる。
「なぜその土地に、その芸能がなければならなかったのか」をもう一度多視点から考えてみることで、地域の活性化の活路を見出せるかもしれない、と一郷土芸能ファンは思うのである。
芸能は文化芸術なのか
全国各地で「芸術祭」が盛んに開催されている。単にアーティストの作品を展示するだけではなく、その土地の特徴を活かした様々な取り組みがなされ、「芸術・アート」の姿を借りて存在しているかのようだ。
郷土芸能も負けてはいない。その土地の風土や人、性格といった文化的背景が、芸能の踊りや振りや仕草、装束の色や道具といった「芸術」的な形となって表れている。あるいは、東北地方を代表する芸能「早池峰神楽」は山伏修験が布教のために行っていた神楽だが、この神楽の最高神(仏)は「権現様」という真っ黒な獅子頭。これは、神仏が「権=仮」の姿である獅子頭を使って世の中に「現」れたという状態を示していて、本来伝えたかったものを借りの姿で表現しているものと考えられる。
その土地に住まう人々が伝えていくべき思いを最も如実に表し、かつ注目を集める存在として、郷土芸能は大きな役割を果たすもの。その地に存在するあらゆるもの、風土やくらし、食、生業などのさまざまなシチュエーション全てに対応できるオールマイティーな役者が「郷土芸能」であり、基本さえしっかり体に染み付かせておけば、どんな舞台に出しても恥ずかしくはない。
昨年8月、岩手県の三陸沿岸地方を中心に行われた「三陸国際芸術祭」(主催:NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク 共催:(公社)全日本郷土芸能協会)は、タイトルこそ「芸術祭」としているが、岩手県を中心に、海の向こうからも芸能が集った「郷土芸能祭」であった。
私は郷土芸能の分野でのプログラムディレクターとして関わったが、東北の厳しさと豊かさを身に宿した多種多様の郷土芸能たちが、太平洋の大海原を背に、雷雲たちこめる大空を頭上に、草や木々が根を張る黒々とした大地の土を足下に感じながら、踏みしめ、跳躍し、奏で、歌う姿に触れ、大きな自信と誇りを得ることができた。そこは、海を越えてやってきたバリ・韓国の芸能や、コンテンポラリーダンス・サイトスペシフィックダンス・コミュニティダンスといった、郷土芸能とは一線を画されてきた「文化芸術」が出会う場であった。私はこの企画に、それぞれが同じ海、空、大地の上で見て感じることで、芸能やダンスの「表現」の形と、それらを積み重ね作り上げてきた郷土や先人に誇りを持ってもらいたいとの願いを込めていた。
また、先日2月1日には、宮城県のせんだいメディアテークで開催された第3回国連防災世界会議直前イベントにおいて、「被災地・被災者に対し文化・芸術が何を果たしたのか、何が出来るのか?」という問いに迫るイベントが開催された。『ひとのちから~祈りを奏でる、祈りをおどる~』と題し、(公財)音楽の力による復興センター・東北が企画制作したものである。
震災からこれまで、さまざまなジャンルの芸術文化に関わる人たちが、それぞれのやり方で、それぞれの場所から、亡くなられた方々へ祈り、歌や踊りを通して慰め、励ましてきた。それは録音されたもの、録画された映像ではなく、その時、その場にたたずんで初めて湧き出す思いを踊りや歌といった人が持つ能力で伝えよう、昇華しようとした表れである。こうしたものが継続的な祈りへと繋がって今の芸能や祭りが出来てきたのかもしれないと、そのルーツを追体験するかのような新たな視点を持った企画であった。今回私は鎮魂供養を担う郷土芸能「鹿踊」を紹介することで関わったのだが、鹿踊の圧倒的なパフォーマンスや装束の意匠の奥にある、芸能の神髄を、多くの人たちに共感してもらえた内容になったのではないだろうか。
郷土芸能が文化芸術ではないとか、相容れないなどという先入観は、一体誰が決めたのだろう??
芸能は「ため」になるのか
文化芸術は、震災から人や地域が復興していく「ため」になるのか、役に立つのか。文化芸術に携わる人たちの多くが突きつけられた問いである。
実際「文化の力が被災者にとって,復興に向けて前向きに生きていく原動力となった」、「地域の民俗芸能をいち早く復興させたことが地域コミュニティの再構築につながった」、「被災文化財等の救出を通じて、「地域のたから」の有り難さを実感し、地域のアイデンティティーの意義を再認識した」などの報告がなされている(最近の情勢と今後の文化政策 (提言)~東日本大震災から学ぶ、文化力による地域と日本の再生~ 平成24年9月28日 文化審議会文化政策部会 より)。このように、郷土芸能が文化芸術活動として人や地域を励まし、つなぎ、コミュニティを再構築させるという成果をあげたのだが、このことが文化芸術を核とした地域活性化も可能であるという一つの事例となったのではないか。
芸能や祭りに関わることで、住む人も、離れた人も、外から行く人も、活き活きし、地域が輝いて見える。被災地で、確かにその光景を見ることが出来た。
昨年の山梨や徳島の雪害、長野県北部の地震、広島県の土砂災害や御嶽山の噴火等、自然災害は後を絶たない。自然の脅威を身近に感じる機会が徐々に多くなっている気がする。また、止まらぬ過疎少子高齢化、団塊世代の定年、東京オリンピックへ向けての動き等、郷土芸能を取り巻く環境は新たな局面を迎えようとしている。なぜ、郷土芸能がこの災害大国日本に多数存在し、したたかに生き延びてきたのだろうか。さらに深く気づき、考えていこう。

http://www.jfpaa.jp/ (全日本郷土芸能協会)
http://to-shika.tumblr.com/ (東京鹿踊)
 ご覧のページは、これまでのコンソーシアムのホームページを活用し、コンソーシアムの活動記録や資料等をアーカイブ化したものになります。
ご覧のページは、これまでのコンソーシアムのホームページを活用し、コンソーシアムの活動記録や資料等をアーカイブ化したものになります。