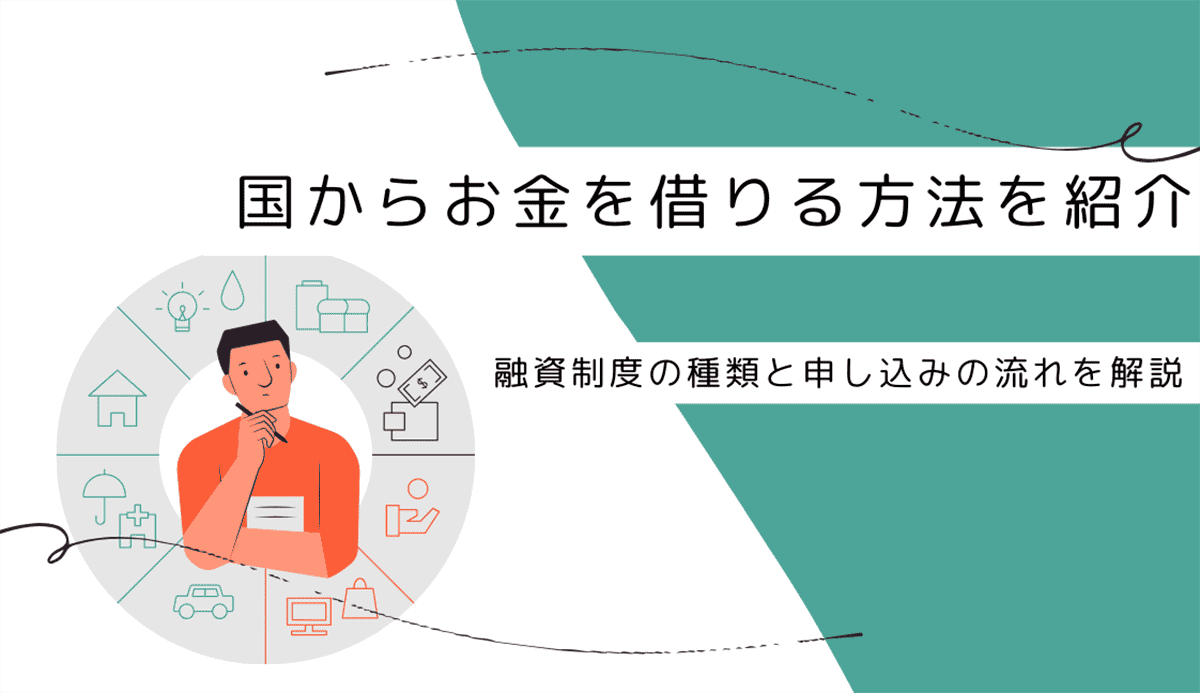生活に困っているときや進学のお金が足りない人は、国からお金を借りると少ない利息の負担で借入可能です。
国の融資制度は借入目的に合わせて資金の種類を選び、自分で申し込まなければいけません。
資金の種類が多く、適切な借入先を探すのも難しいです。
必要に応じて資金を選べるよう、国からお金を借りる公的融資制度の種類を解説。
申し込みの流れも紹介するので、制度の利用を検討している人は参考にしてください。
国からお金を借りる公的融資制度の借入目的別一覧!自分に合うものを利用して乗り切りる
国からお金を借りる公的融資制度には、以下の種類があります。
| 借入目的 | 公的融資制度 | 融資対象者 | 相談先 |
|---|---|---|---|
| 生活関連資金 | 生活福祉資金貸付制度 | ・低所得世帯 ・高齢者世帯 ・障害者世帯 |
社会福祉協議会 |
| 緊急小口資金貸付 | 緊急に生活を維持するお金が必要な世帯 | 社会福祉協議会 | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付制度 | ・ひとり親家庭の親 ・ひとり親家庭の子ども ・寡婦 |
地方公共団体の福祉担当窓口 | |
| 生活関連資金 ※給付 |
生活保護制度 | 収入が最低生活費に満たない家庭 | 福祉事務所の生活保護担当 |
| 教育関連資金 | 国の教育ローン(日本政策金融公庫の教育一般貸付) | 指定の学校に在学中または進学予定の学生、親 | 日本政策金融公庫 |
| 日本学生支援機構の奨学金 | 以下の国内機関で学ぶ人 ・大学 ・短期大学 ・高等専門学校 ・専修学校(専門課程) ・大学院 |
日本学生支援機構 | |
| 看護師等修学資金貸与制度 | 以下の養成施設または大学院に在学している人 ・保健師 ・助産師 ・看護師 ・准看護師 |
進学先の養成施設 | |
| 失業中の生活資金 事業資金 |
求職者支援資金融資制度 | 雇用保険を受給できない離職者 | ハローワークで手続き後労働金庫から借り入れ |
| 臨時特例つなぎ資金貸付制度 | 住居のない離職者 | 社会福祉協議会 | |
| 事業資金 | 日本政策金融公庫の融資制度 | ・個人事業主 ・法人 ・農林漁業者 |
日本政策金融公庫 |
| 住宅資金 | 住宅金融支援機構のフラット35 | 住宅取得者 | 住宅金融支援機構と提携した金融機関 |
公的融資制度は、お金を借りる目的によって制度が分かれます。
融資対象となる人も詳細に決められているため、自分に合う制度を選んで利用しなければいけません。
生活関連資金を借りるなら、生活福祉資金貸付制度や母子父子寡婦福祉資金貸付が向いています。
教育関連資金は、国の教育ローンや奨学金で借入可能です。
失業中の人や、事業目的でお金を借りたい人向けの融資制度もあります。
目的に合う融資制度を活用して、お金のない時期を乗り切りましょう。
生活関連資金の足りない個人や世帯が利用できる公的融資制度
生活関連資金の足りない個人や世帯が利用できる公的融資制度は、以下の通りです。
- 生活福祉資金貸付制度
- 緊急小口資金
- 母子父子寡婦福祉資金貸付
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や高齢者世帯を対象とした融資です。
資金の種類が決まっていて、借入目的に合わせて利用します。
緊急小口資金は急いでお金を借りなければいけない人向けで、他の資金より早めの借り入れも可能です。
母子父子寡婦福祉資金貸付は、ひとり親家庭や寡婦が利用できます。
融資制度では生活を立て直せないなら、生活保護制度も考えましょう。
生活保護を受けると生活に制限もあります。
融資制度で乗り切れるなら乗り切って、難しい時に生活保護制度を活用しましょう。
生活福祉資金貸付制度は生活や福祉目的でお金が借りられる
生活福祉資金貸付制度は、以下の人が借り入れできる公的融資制度です。
- 必要な資金を他から借りるのが難しい低所得者世帯
- 障害者手帳の交付を受けた人が属する障害者世帯
- 65歳以上の高齢者が属する高齢者世帯
低所得者世帯とは、市町村民税非課税程度の世帯です。
住民税の計算方法は住んでいる自治体によって異なります。
大阪市に住んでいる人なら、住民税非課税になるのは以下の金額です。
- 3人家族なら年収256万円未満
- 4人家族なら年収306万円未満
住民税非課税世帯に該当するかわからないときは、市町村役場に問い合わせましょう。
資金ニーズに応じて融資できるよう、生活福祉資金貸付制度では4つの資金が用意されています。
- 総合支援資金
- 福祉資金
- 教育支援資金
- 不動産担保型生活資金
失業や減収などによる生活困窮が広がっている中、生活に困窮したかたに対し、生活を立て直せるよう支援することが求められています。そこで、低所得者などに対するセーフティネット施策の一つである生活福祉資金貸付制度について、利用者にとって分かりやすく、資金ニーズに応じた柔軟な貸付けを行うことができるよう、平成21年10月から、資金の種類を4つに整理・統合するとともに、貸付利子を引き下げるなどの改正が行われました。
出典:生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付制度」があります。│政府広報オンライン
2009年から利子も引き下げられ、以下の利率で借入可能です。
| 状況 | 利子 |
|---|---|
| 連帯保証人あり | 無利子 |
| 連帯保証人なし | 年1.5% |
※教育支援資金と緊急小口資金は無利子
連帯保証人を用意できれば、無利子で借りられます。
連帯保証人がいなくても、年1.5%と低金利です。
平均金利が年18.0%の消費者金融で借りたときと、利息を比較しましょう。
| 借り方 | 生活福祉資金貸付制度 | 消費者金融 |
|---|---|---|
| 10万円借りて2年で返済 | 1,600円程度 | 19,800円程度 |
| 20万円借りて4年で返済 | 6,200円程度 | 82,000円程度 |
参考:カードローンのかんたん返済額シミュレーション│E-LOAN
生活に困っている人向けの制度のため、利息がほとんどかかりません。
生活福祉資金貸付制度は、借り入れまでに1ヶ月程度かかります。
融資条件に当てはまる世帯は、時期的な余裕を持って社会福祉協議会に相談しましょう。
総合支援資金は生活再建や住居費に借りたお金を使える
総合支援資金の内容は、以下の通りです。
| 資金の種類 | 貸付限度額 | 据置期間 | 返済期間 |
|---|---|---|---|
| 生活支援費 | ・単身世帯:月15万円以内 ・2人以上世帯:月20万円以内 |
最終貸付日から6ヶ月以内 | 10年以内 |
| 住宅入居費 | 40万円以内 | 貸付日から6ヶ月以内 | |
| 一時生活再建費 | 60万円以内 |
据置期間とは、借り入れから返済開始までの期間です。
融資直後に返済が始まると生活を立て直すのが難しいため、返済開始までに猶予を持たせています。
総合支援資金の目的は、生活再建と経済的な自立の促進です。
原則3ヶ月間融資を受けられる生活支援費で、生活の立て直しを目指します。
生活支援費は最大12ヶ月まで延長可能です。
生活支援費でまかなえない費用は、一時生活再建費で用意します。
一時生活再建費の使い道は、以下の通りです。
- 就職活動や技能習得費用
- 家賃や公共料金滞納の一時立て替え
- 債務整理に必要な費用
住宅の契約が必要なら、住宅入居費を活用しましょう。
総合支援資金で借りるには自立相談支援事業を利用しなければいけない
総合支援資金で借りるには、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業を利用しなければいけません。
自立相談支援事業とは、地域の担当者が必要な支援を一緒に考えてくれる制度です。
個人に合う支援プランを作成した上で、就労支援や必要な融資を実施します。
就職が内定している人以外は、相談事業を利用して融資の条件を満たしましょう。
福祉資金は福祉の充実や生計維持に役立てられる資金
福祉費は住環境の整備や、生計維持に役立てる目的で利用します。
| 福祉の充実 | ・住宅の増改築 ・福祉用具の購入 ・障害者用の自動車購入費用 ・福祉用具購入費用 ・介護サービスや障害者サービスに必要な費用 ・災害を受け臨時に必要な費用 ・冠婚葬祭費 |
|---|---|
| 生計維持 | ・生業を営むための資金 ・就職の支度に必要な経費 ・技能習得費用 ・技能習得中の生計維持 |
福祉資金の内容は、以下の通りです。
| 資金の種類 | 貸付限度額 | 据置期間 | 返済期間 |
|---|---|---|---|
| 福祉費 | 580万円以内 | 貸付日から6ヶ月以内 | 20年以内 |
福祉用具の購入やサービスの利用、冠婚葬祭費といった目的に借りたお金を使えます。
融資額の上限は最大580万円までで、お金の使い道によって上限額が設定される仕組みです。
必ずしも、全員が580万円受け取れるわけではありません。
就職活動で必要な費用が3万円なら、最大で3万円まで受け取れます。
お金の利用目的別によって何円まで借りられるか、社会福祉協議会で確認しましょう。
教育支援資金は入学時や月々の学費に借りたお金を使える
教育支援資金の内容は、以下の通りです。
| 資金の種類 | 貸付限度額 | 据置期間 | 返済期間 |
|---|---|---|---|
| 教育支援費 | ・高校:月3万5千円以内 ・高専:月6万円以内 ・短大:月6万円以内 ・大学:月6万5千円以内 |
卒業から6ヶ月以内 | 20年間 |
| 就学支度費 | 50万円以内 |
毎月必要な学費は教育支援費で借ります。
通学する学校によって、3万5,000円~6万5,000円の範囲で融資可能です。
特に必要と認められれば、決められた金額の1.5倍まで借り入れできます。
増額が必要と認められるには、以下の条件を満たさなければいけません。
- 進学先の学費が現行の貸付限度額では足りない
- 借入申込者が進学に対する熱意や将来への計画性を有している
条件を満たしていると社会福祉協議会によって確認されれば、増額できます。
入学の際に必要な以下の資金は、就学支度費で借りる仕組みです。
- 入学金
- 教科書代
- 制服代
- 通学鞄代
- 通学用自転車購入費用
20年以内に返済を済ませればよく、余裕を持って借りたお金を返せます。
教育支援資金は、連帯保証人の有無にかかわらず無利子で借りられる資金です。
ただし世帯内で連帯借受人を立てなければいけません。
教育支援資金は原則学生が申込者となります。
連帯借受人は生計を立てている人で、学生の保護者です。
連帯借受人
借受者と連帯して債務を負担する方です。原則として借受人の世帯の生計中心者となります。修学資金(高校進学)を例に取りますと申込者は高校に進学を希望する方で、原則として保護者の方が連帯借受人になります。
出典:連帯保証人・連帯借受人とは?│相模原市社会福祉協議会
教育支援資金を利用する際は、学生と保護者が納得した上で融資を受けましょう。
不動産担保型生活資金はまとまったお金を借りたいときに利用できる
不動産担保型生活資金はまとまったお金も借りられる公的融資制度で、高齢者世帯のみ利用できます。
不動産を担保にし、まとまった高額融資を受けられる制度。
融資の内容は、以下の通りです。
| 資金の種類 | 貸付限度額 | 据置期間 | 返済期間 |
|---|---|---|---|
| 不動産担保型生活資金 | ・土地評価額の70%程度 ・月30万円以内 |
契約終了から3ヶ月以内 ※契約期間は申込者の死亡時または貸付限度額に達するまで |
7年間 |
| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | ・土地評価額の70%程度 ・生活扶助額の1.5倍以内 |
借りたお金は生活資金として利用可能です。
借りられる金額は土地評価額を元に決定されます。
土地評価額の70%に達すると、以降の借り入れはできません。
不動産担保型生活資金の利子は他の融資と異なり、以下のいずれか低い利率を適用します。
- 年3.0%
- 長期プライムレート
長期プライムレートとは、金融期間が1年以上の期間にわたって融資する際の金利です。
一般に、「長期プライムレート」とは、金融機関が優良企業向けの長期貸出(1年以上の期間の貸出)に適用する最優遇金利、「短期プライムレート」とは、金融機関が優良企業向けの短期貸出(1年未満の期間の貸出)に適用する最優遇金利のことを指します。
出典:日本銀行について│日本銀行
令和元年から令和5年にかけての長期プライムレートは、年0.95~1.50%の範囲を推移しています。
参考:長・短期プライムレート(主要行)の推移│日本銀行
上記を参考にすると、不動産担保型生活資金は金利0.95%~最大3.0%までと非常に低金利。
長期プライムレートが低いので、金利1.5%前後で借りられる可能性があります。
不動産担保融資は担保となる不動産がある人のみ、利用できます。
活用できる不動産があるなら、利用しましょう。
緊急小口資金は緊急でお金が必要なときに無利子で借りられる少額の資金
緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生計が維持できなくなった人向けの少額融資です。
| 貸付限度額 | 10万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 貸付日から2ヶ月以内 |
| 返済期間 | 1年以内 |
貸し付けを受けられるのは、10万円までです。
借りたお金は2ヶ月間の据置期間ののち、1年以内に返済しなければいけません。
緊急小口資金は福祉資金に分類される費用ですが、他の融資と以下の点で異なります。
- 無利子
- 融資までの期間が1週間程度
他の資金を借りる際、連帯保証人を付けられなければ年1.5%の利息が発生します。
緊急小口資金は緊急性が高い資金のため、連帯保証人の有無に関わらず無利子です。
借り入れまでの待ち時間も短く、1週間程度で借りられます。
他の資金出融資を受けるには、1ヶ月程度の時間が必要です。
急いで借りなければ生活できないときは、緊急小口資金を利用しましょう。
母子父子寡婦福祉資金貸付制度はひとり親家庭向けで低金利
母子父子寡婦福祉資金貸付制度は、以下の家庭向けの公的融資制度です。
| ひとり親家庭 | 20歳未満の児童を扶養する配偶者のない男性または女性 ※資金によっては子どもも借入可能 |
|---|---|
| 寡婦 | 以下のいずれかに当てはまる ・子ども以外の扶養親族がいて配偶者と死別、離婚、生死不明 ・扶養親族なしで配偶者と死別、生死不明 |
ひとり親以外に、寡婦も融資を受けられます。
寡婦とは、子ども以外の扶養親族がいて配偶者と死別または離婚している女性です。
扶養親族がいなくても、配偶者と死別または離婚していれば寡婦に当たります。
資金の種類は以下の通りです。
| 資金の種類 | 融資額 | 融資対象者 | 金利 |
|---|---|---|---|
| 事業開始資金 | 3,140,000円 | ・ひとり親家庭の親 ・寡婦 |
・連帯保証人あり:無利子 ・連帯保証人なし:年1.0% |
| 事業継続資金 | 1,570,000円 | ||
| 技能習得資金 | ・月額68,000円 ・運転免許:460,000円 |
||
| 生活資金 | ・一般:月学105,000円 ・技能:月額141,000円 |
||
| 住宅資金 | 1,500,000円 | ||
| 転宅資金 | 260,000円 | ||
| 結婚資金 | 300,000円 | ||
| 修学資金 | 月額52,500円~183,000円 | ・ひとり親家庭の子ども ・父母のいない子ども ・寡婦の子ども |
無利子 ※家庭内で連帯借受人または連帯保証人をつける |
| 修業資金 | 月額68,000円 | ||
| 就学支度資金 | 64,300円~590,000円 | ||
| 就職支度資金 | 100,000円 | ・ひとり親家庭の親 ・寡婦 ・ひとり親家庭の子ども ・父母のいない子ども ・寡婦の子ども |
【親への貸し付け】 ・連帯保証人あり:無利子 ・連帯保証人なし:年1.0% ※子どもへの貸し付け ・無利子 ・家庭内で連帯借受人または連帯保証人をつける |
| 医療介護資金 | ・医療:340,000円 ・介護:500,000円 |
・ひとり親家庭の親 ・寡婦 ・ひとり親家庭の子ども ・寡婦の子ども |
・連帯保証人あり:無利子 ・連帯保証人なし:年1.0% |
必要に応じて、資金の種類を選んで借り入れをする仕組みです。
資金の種類によって、融資対象者や金利が違います。
母子父子寡婦福祉資金貸付制度は、生活福祉資金貸付制度と比較してより低金利で借入可能です。
| 資金の種類 | 金利(年) | 事業開始資金として借りた100万円を 5年間で返済したときの利息 |
|---|---|---|
| 生活福祉資金貸付制度 | ・連帯保証人あり:無利子 ・連帯保証人なし:年1.5% |
38,600円程度 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付制度 | ・連帯保証人あり:無利子 ・連帯保証人なし:年1.0% |
25,600円程度 |
参考:カードローンのかんたん返済額シミュレーション│E-LOAN
母子父子寡婦福祉資金貸付制度の負担が、より少ないです。
条件に合っている人は、母子父子寡婦福祉資金貸付制度で借りましょう。
生活が成り立たなければ生活保護制度で国から給付を受ける
公的融資制度や給付金を活用しても生活が成り立たなければ、生活保護制度の申請をしましょう。
生活保護を受けるには、以下の条件があります。
- 預貯金や生活に利用していない土地家屋を活用する
- 能力に応じて働く
- 生活保護よりも先に手当や年金の受給を申し込む
- 身内の頼れる人は援助を受ける
すべての条件を満たしても得られるお金が最低生活費に達しなければ、生活保護を受けられます。
最低生活費とは厚生労働大臣が定める基準で計算した、生活に最低限必要な金額です。
住んでいる土地によって物価が変わるため、地域や家族の人数を元に計算します。
生活保護で支給を受けられるのは、最低生活費から収入を引いた金額です。
最低生活費が15万円、収入が8万円の人は、生活保護費として7万円支給されます。
収入に含まれるのは、以下のお金です。
- 仕事で稼いだ収入
- 親族からの援助
- 手当や年金
生活保護は働きながらでも受給できます。
生活が成り立たないほど苦しいときは、福祉事務所の生活保護担当に相談しましょう。
生活保護で支給を受けられる費用の内訳
生活保護で支給を受けられる費用には、以下の種類があります。
| 費用の種類 | 内容 | 支給方法 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 日常生活を送るための費用 | 定められた計算方法で計算して算出 |
| 住宅扶助 | アパートの家賃 | 決められた上限の範囲内で実費を支給 |
| 教育扶助 | 義務教育を受けるための費用 | 決められた基準額を支給 |
| 医療扶助 | 医療サービス費用 | 本人負担なしでサービスの提供元に直接支払い |
| 介護扶助 | 介護サービス費用 | |
| 出産扶助 | 出産に必要な費用 | 決められた上限の範囲内で実費を支給 |
| 葬祭扶助 | 葬祭費用 | |
| 生業扶助 | 就労を目的とした技能習得に必要な費用 |
医療サービスや介護サービスを受けると、サービスの提供元に直接料金が支払われます。
出産費用や葬祭費用は実費での支給が可能です。
必要に応じてお金を受け取れるよう、ケースワーカーの調査に協力しましょう。
教育関連費用を借りたい人向けの公的融資制度は主に3種類
教育関連費用を借りたい人向けの公的融資制度は、以下の3種類です。
| 公的融資制度 | 借りられる人 |
|---|---|
| 国の教育ローン | ・学生の保護者 ・安定した収入があり独立して生計を営んでいる学生 ※進学予定の人も含む |
| 日本学生支援機構の奨学金 | 学生 |
| 看護師等修学資金貸与制度 | 助産師や看護師を目指す学生 |
国の教育ローンは、主に学生の保護者が借り入れできる制度です。
進学予定の人も含めて借りられるローンなので、受験費用に充てたいときにも活用しましょう。
日本学生支援機構の奨学金や看護師等修学資金貸与制度は、学生本人が借り入れをする制度です。
看護師等修学資金貸与制度は助産師や看護師を目指す学生向けで、利用できる人が限定されます。
借りたお金は、将来返済しなければいけません。
学生が借りるときは、返済も意識した上で申し込みましょう。
国の教育ローンでは受験費用も含めて教育費を用意できる
国の教育ローンは進学前の人も融資の対象で、受験費用も含めて教育費を用意できる制度です。
正式名称は教育一般貸付で、国の金融機関である日本政策金融公庫が提供しています。
融資条件は以下の通りです。
| 上限額 | 350万円(一定の要件を満たせば450万円まで) |
|---|---|
| 金利(年) | 1.95% |
| 返済期間 | 最長18年間 |
| 借りた費用の使い道 | ・受験費用 ・受験時の交通費や宿泊費用 ・入学金 ・施設設備費 ・教材費 ・授業料 ・定期代 ・在学のためのアパート代 ・パソコン購入費 ・修学旅行費用 ・学生の国民年金保険料 |
| 融資対象の学校 | ・大学院 ・大学院 ・短期大学 ・高等学校 ・高等専門学校 ・専門学校 ・予備校 ・デザイン学校 ・語学学校 ・職業能力開発校 |
| 利用できる人の条件 | 保護者の年収(所得)が制限以内 ・子ども1人:790(600)万円 ・子ども2人:890(690)万円 ・子ども3人:990(790)万円 ・子ども4人:1,090(890)万円 ・子ども5人:1,190(990)万円 |
| 日本学生支援機構の奨学金との併用 | 〇 |
国の教育ローンで借りられる上限額は、350万円です。
以下の条件に当てはまると、450万円まで借りられます。
- 自宅外通学をする
- 修業年限5年以上の大学に通う
- 大学院に通う
- 修業年限3ヶ月以上の外国教育施設に海外留学する
金利は年1.95%で、最長18年間かけて計画的に返済できます。
最高額350万円を借りて18年間かけて返済したときのシミュレーション結果は、以下の通りです。
| 月々の返済額 | 19,400円 |
|---|---|
| 返済総額 | 4,149,800円程度 |
| 保証料 | 194,100円程度 |
無理なく返済できるか、事前にシミュレーションしましょう。
借りたお金は幅広い目的に利用でき、在学前の受験関連費用も借りられます。
対象となる学校も、国内外含めて幅広いです。
融資の対象とならない条件は、以下の通り。
| 条件 | 対象の学校 |
|---|---|
| 研究生や聴講生として授業に参加している | すべての学校 |
| 学生が公務員として通っている | ・防衛大学校 ・防衛医科大学校 ・航空保安大学校 ・海上保安学校 ・海上保安大学校 ・気象大学校 ・税務大学校 |
| 企業内教育訓練施設に通っている | ・学費がかからない企業内学校 ・特定企業の従業員が給与を受けながら教育や訓練を受ける学校 |
国の教育ローンは、以下の条件を満たせば学生本人も申し込めます。
- 安定収入がある
- 独立して生計を営んでいる
融資の条件を満たしている人は、国の教育ローンを活用して教育費を用意しましょう。
世帯の状況によっては優遇制度もある
国の教育ローンには、以下の優遇制度があります。
| 条件 | 優遇の内容 |
|---|---|
| ・ひとり親家庭 ・交通遺児家庭 ・子ども3人以上で年収500万円(所得356万円)以内 |
・金利引き下げ(年1.55%) ・保証料が通常の半額 |
| 世帯年収200万円(所得132万円)以内 | 金利引き下げ(年1.55%) |
世帯の状況や収入によって、金利引き下げや保証料半額の優遇を受けられます。
保証料は返済期間や借入額によって変動する仕組みです。
融資額100万円で返済期間5年間のときは、15,600円程度かかります。
優遇される家庭の人は、制度を利用して少ない負担で借りましょう。
日本学生支援機構の奨学金は学生本人が教育費用を借り入れできる
日本学生支援機構の奨学金は、学生本人が利用できる公的融資制度です。
教育基本法に定める「教育の機会均等」の理念を叶えられるよう、経済的理由で進学が難しい学生に学費の給付や貸与を行います。
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
出典:教育基本法│文部科学省
利用できる奨学金の種類は、進学先の学校や保護者の年収で決まる仕組みです。
海外留学に利用するなら、海外留学のための奨学金を利用しましょう。
国内で利用できる奨学金は、以下の3種類です。
| 奨学金の種類 | 返済 | 利息 |
|---|---|---|
| 給付奨学金 | 不要 | ― |
| 貸与奨学金(第一種奨学金) | 必要 | なし |
| 貸与奨学金(第二種奨学金) | 必要 | あり |
給付奨学金には、返済義務がありません。
返済義務のある貸与奨学金には、無利子の第一種奨学金と、利子のつく第二種奨学金があります。
奨学金の家計目安を計算する式は、複雑です。
該当する奨学金の種類を調べたいときは、「進学資金シミュレーター」を活用しましょう。
奨学金の申し込み方法は申し込む時期で異なる
奨学金の申し込み方法は、以下の通りです。
| 申し込みのタイミング | 申込方法 |
|---|---|
| 進学前(予約採用) | 在学する高校で説明を受けた後必要書類提出 |
| 進学後(在学採用) | 在学する学校で必要書類を受け取って提出 |
進学前に手続きを済ませるなら、在学中の高校で説明を受け、必要書類を提出します。
進学後に申し込みたいときは、在学する学校で必要書類を受け取りましょう。
看護師等修学資金貸与制度は助産師や看護師を目指す学生が借りられる
看護師等修学資金貸与制度は、以下の養成施設または大学院に在学している学生が借りられる公的融資制度です。
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
借りられる金額は地域によって異なり、例えば京都府では以下の通りです。
| 目指す職業 | 国公立の養成施設に在学する学生 | 私立の養成施設に在学する学生 |
|---|---|---|
| ・保健師 ・助産師 ・看護師 |
32,000円 | 36,000円 |
| 准看護師 | 15,000円 | 21,000円 |
※月額
看護師等修学資金貸与制度の目的は、不足しがちな看護師や助産師の確保です。
制度の目的を果たせるよう、融資を受けるには以下の条件を満たさなければいけません。
- 卒業後に地域が定める返還免除対象施設で所定の期間以上継続して仕事に従事する
- 経済的理由で進学が困難である
- 同じ趣旨の奨学金を借りていない
この制度は、保健師、助産師、看護師又は准看護師を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者、及び大学院の修士課程において看護に関する専門知識を修得しようとする者に修学資金を貸与し、もってこれらの者の修学を容易にすることにより、貸与事業実施主体が管轄する地域内の保健師、助産師、看護師及び准看護師の確保及び質の向上に資することを目的とする。
参考:看護師等修学資金の貸与について│厚生労働省
条件は都道府県によって異なります。
就職予定の地域の制度を確かめて、条件を確認した上で利用しましょう。
看護師等修学資金貸与制度には返還免除がある
看護師等修学資金貸与制度で借りたお金は、卒業後県内の定められた返還免除対象施設で決められた期間業務に就くと、返還が免除されます。
働く期間も都道府県によって異なり、群馬県では5年間です。
東京都では貸与月額に応じて、5年~7年働く必要があります。
継続して仕事に就けば免除が認められる可能性もあるため、条件を確認して返還免除を受けましょう。
無職の人が再就職を目指して借りられる資金2つ
無職の人が再就職を目指して活動する間に借りられる資金は、以下の2つです。
- 求職者支援資金融資制度
- 臨時特例つなぎ資金貸付制度
求職者支援資金融資制度は、雇用保険を受給できない求職者向けの融資制度です。
職業訓練受講給付金を受けながら職業訓練に参加している人が、融資を受けられます。
臨時特例つなぎ資金貸付制度は、住居のない離職者向けの制度です。
公的融資制度や公的給付制度の利用が決まっていても、当面の生活が成り立たないケースもあります。
融資や給付が受けられるまでの措置として、一時的に借り入れできる資金です。
無職で収入がなくても、公的給付制度なら借りられる可能性があります。
状況に合わせて借り入れしましょう。
求職者支援資金融資制度は雇用保険を受給できない求職者が借りられる
求職者支援資金融資制度は、雇用保険を受給できない求職者向けの公的給付制度です。
雇用保険に加入していた労働者が離職すると、雇用保険の基本手当(失業保険)を受けられます。
しかし以下の人は失業保険の対象となりません。
- 雇用保険に加入していない人
- 離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以下
個人事業主や同居の親族は、原則雇用保険に加入できません。
1週間の所定労働時間が20時間以下の人や、雇用期間31日未満の人も雇用保険の対象外です。
失業保険の対象にならない人は、求職者支援制度を利用できます。
- 無料の職業訓練を受けられる
- 就職サポートを受けられる
- 月10万円の職業訓練受講給付金がもらえる
月10万円の職業訓練受講給付金で生活が成り立つなら、求職者支援資金融資制度は必要ありません。
給付金を受けても訓練受講中の生活費が不足するときに融資を受けられるのが、求職者支援資金融資制度です。
融資の内容は以下の通り。
| 融資額 | 月5万円または10万円 |
|---|---|
| 融資期間 | 職業訓練を受講する月数 |
| 金利(年) | 3.0% |
| 担保と保証人 | 不要 |
求職者支援資金融資制度を利用する流れ
求職者支援資金融資制度を利用する流れは、以下の通りです。
- ハローワークで職業訓練受講給付金の決定を受ける
- ハローワークで求職者支援資金融資要件確認書の交付を受ける
- 労働金庫で借り入れの手続きをする
ハローワークで認定を受けた後、労働金庫で借り入れの手続きをする流れでお金を借りましょう。
臨時特例つなぎ資金貸付制度は住居のない離職者が利用できる
臨時特例つなぎ資金貸付制度は、住居のない離職者を対象とした公的融資制度です。
公的貸付制度や公的給付制度を申請していても、貸し付けや支給が始まるまでの生活が成り立たないときに、利用できます。
対象となる制度は、以下の通りです。
- 生活福祉資金貸付制度
- 失業給付
- 住居確保給付金
生活福祉資金貸付制度による融資を受けられる期間は、緊急小口資金でも1週間程度必要です。
失業給付の支給には、会社都合の退職でも1ヶ月程度かかります。
住宅確保給付金は家を失う恐れがあるときに、家賃分の支給を受けられる制度です。
支給を受けられるまでには、1ヶ月程度待たなければいけません。
臨時特例つなぎ資金貸付制度の内容は、以下の通りです。
| 融資額 | 10万円まで |
|---|---|
| 金利 | 無利子 |
| 連帯保証人 | 不要 |
| 相談先 | 社会福祉協議会 |
借りられる金額は10万円までで、利息や連帯保証人は必要ありません。
融資や給付が決まっている住居のない離職者で生活の成り立たない時期があるなら、社会福祉協議会に相談しましょう。
日本政策金融公庫の融資制度は個人事業主や法人が事業目的で申し込める
日本政策金融公庫では、事業融資も扱っています。
事業融資の内容は、以下の通りです。
| 事業の内容 | 融資対象者 | 特徴 |
|---|---|---|
| 国民生活事業 | ・小規模事業者 ・個人事業主 |
・融資残高の平均は約1,000万円 ・短期の運転資金も融資可能 |
| 中小企業事業 | 中小企業 | ・融資残高の平均は約1.3億円 ・短期の運転資金は融資不可 |
| 農林水産事業 | 農林水産業者 | 長期事業資金を借りられる |
企業規模や従事している事業によって、利用できる融資制度が異なります。
小規模事業者や個人事業主向けの融資事業が、国民生活事業です。
中小企業は中小企業事業を利用します。
農林水産業者は、農林水産事業を利用する仕組みです。
自社に適した融資事業を利用して、事業資金を借りましょう。
国から1,000万円借りるなら国民生活事業
小規模事業者や個人事業主が借り入れをする国民生活事業では、1,000万円程度の資金を借りられます。
・ご融資残高の平均は約1,000万円です。
・短期の運転資金も取扱可能です。
出典:融資制度を探す│日本政策金融公庫
国民生活事業では、以下の目的で資金を借りられます。
- 新事業活動に取り組む
- 事業拡大や生産性向上を図る
- 事業承継に取り組む
- 保育・介護や社会的課題の解決を目的として事業を営む
- 海外展開を図る
- 環境対策を促進する
- 一時的に業況が悪化しているため対策をする
- 事業の再建を図る
特定の目的がないときは、一般貸付を利用します。
一般貸付の融資内容は、以下の通りです。
| 融資限度額 | ・運転資金、設備資金:4,800万円 ・特定設備資金:7,200万円 |
|---|---|
| 金利(年) | 1.94~2.40% |
| 返済期間 | 5年~20年間 |
| 担保と保証人 | 申込者と相談しながら設定 |
一般貸付はほとんどの業種の小規模事業者が融資を受けられます。
資金を調達する目的に合わせて、申し込む資金を決めましょう。
日本政策金融公庫の公式サイトは、融資制度の検索にも対応しています。
日本政策金融公庫には起業を目指す人向けの融資制度もある
日本政策金融公庫には、起業を目指す人向けの融資制度もあります。
一般のビジネスローンでは、開業資金の調達が難しいです。
資金使途 事業資金(開業資金は含みません)
出典:レイク de ビジネス│レイク
ビジネスローンは申込時点で事業を営んでいる人向けの商品のため、一部の開業向けローンしか利用できません。
日本政策金融公庫には、以下の融資制度があります。
| 融資制度 | 新規開業資金 | 新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連) | 新規開業資金(再挑戦支援関連) | 新規開業資金(中小企業経営力強化関連) |
|---|---|---|---|---|
| 融資対象者 | ・新たに事業を始める人 ・事業開始後おおむね7年以内の人 |
新たに事業開始または事業開始後おおむね7年以内で以下のいずれかに当てはまる人 ・女性 ・35歳未満の人 ・55歳以上の人 |
新たに事業開始または事業開始後おおむね7年以内で以下のすべてに当てはまる人 ・廃業歴のある個人または廃業歴のある経営者が営む法人である ・廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理されている ・廃業の理由や事情がやむを得ないものである |
新たに事業開始または事業開始後おおむね7年以内で以下のいずれかを適用予定の人 ・中小企業の会計に関する基本要領 ・中小企業の会計に関する指針 ※自ら事業計画書の策定を行い認定経営革新等支援機関による指導や助言を受けている |
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 金利(年) | 2.24~3.20% | 1.34~2.80% | 2.24~3.20% | 1.84~2.80% |
| 返済期間 | 7年~20年間 | 7年~20年間 | 15年~20年間 | 7年~20年間 |
| 担保と保証人 | 申込者と相談しながら設定 | 申込者と相談しながら設定 | 申込者と相談しながら設定 | 申込者と相談しながら設定 |
借り入れをする人の状況によって、金利や返済期間が優遇されるケースもあります。
開業資金を借りる際は、自分に合う融資制度を選んで申し込みましょう。
借り入れをする人の状況によって、金利や返済期間が優遇されるケースもあります。
開業資金を借りる際は、自分に合う融資制度を選んで申し込みましょう。
住宅金融支援機構と提携の金融機関では住宅ローンフラット35を提供している
国の融資制度で、直接住宅ローンを利用する方法はありません。
住宅金融支援機構と提携した金融機関の住宅ローンなら、利用できます。
住宅金融支援機構とは、国の政策実施機関として住宅政策や経済対策に取り組んでいる機関です。
住宅金融支援機構は、日本国政府が100%全額出資する独立行政法人であり、国の政策実施機関として住宅政策や経済対策に取り組んでいます。
引き続き、我が国の住生活の向上を金融面から支援し、政策実施機能の最大化を図るべく、取り組んでまいります。
出典:2022年度 投資家向け説明資料│住宅金融支援機構
住宅金融支援機構と提携金融機関が提供している住宅ローンは、フラット35です。
フラット35は返済終了まで金利が変動しない商品で、返済計画が立てやすくなっています。
商品概要は以下の通りです。
| 申込年齢 | 70歳未満 |
|---|---|
| 融資額 | 100万円~8,000万円 |
| 借入期間 | 15年~35年 |
| 金利(年) | 1.33~3.09% ※借入金受取時に決定 |
| 保証人 | 不要 |
| 保証料、繰り上げ手数料 | 不要 |
| 取り扱い金融機関 | 金融機関一覧 |
フラット35では、保証人も不要です。
繰り上げ返済手数料もかからないため、余裕のあるときは気軽に繰り上げ返済もできます。
金利変動のない住宅ローンを利用したい人は、住宅金融支援機構と提携した金融機関でフラット35に申し込みましょう。
省エネルギー性や耐震性を備えた住宅なら金利が引き下げられる
フラット35では、以下の性能を備えた住宅に対して借り入れすると金利が引き下げられます。
金利引き下げ特典のついた住宅ローンは、フラット35 Sと呼ばれます。
| 住宅の性能 | 内容 |
|---|---|
| 省エネルギー性 | 高水準の断熱性を備える |
| バリアフリー性 | 移動しやすい環境を整える |
| 耐震性 | 強い揺れでも倒壊を防げる |
| 耐久性、可変性 | 耐久性を有している |
引き下げられる金利は、年0.25~0.50%です。
新築住宅の建設や購入のみではなく、中古住宅の購入時にも借り入れできます。
フラット35 Sの認定を受けるには、第三者の検査機関による検査を通じて、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していなければいけません。
質の高い省エネルギー性や耐震性のある住宅を取得する予定があるなら、金利引き下げを受けましょう。
住宅金融支援機構はコロナ禍の課題やデジタル化への対応を目指す
住宅金融支援機構は今後の課題として以下の内容を挙げています。
- コロナ禍の課題に対応する
- 頻発する自然災害への対応を検討する
- デジタル化に対応する
コロナ禍に対しては、コロナの影響で返済に困っている利用者からの相談や返済方法に応じます。
公的機関として、顧客に寄り添った丁寧な対応を継続する方針です。
自然災害に対しては、災害復興住宅融資を提供しています。
災害復興住宅融資とは、災害で被災した人が災害住宅を復旧する目的で借りられる住宅ローンです。
借入申込書を住宅金融支援機構で請求して、取扱金融機関で融資を受けられます。
国民負担の軽減や利便性の向上を目指し、デジタル化の推進にも取り組む予定です。
コロナの影響で困っている人や、災害に遭った人は、利用できる制度がないかチェックしましょう。
国からお金を借りる流れと審査内容
国からお金を借りる流れは、以下の通りです。
- 利用する公的融資制度を選ぶ
- 相談先に連絡を入れる
- 説明後に申込書を提出する
- 審査を受ける
- 融資が決まったら借り入れする
公的融資制度でお金を借りるには、自分で利用したい制度を選ばなければいけません。
利用したい融資制度が決まったら、融資制度を提供している機関に相談しましょう。
生活福祉資金貸付制度や緊急小口資金なら、社会福祉協議会で受け付けています。
母子父子寡婦福祉資金貸付制度なら、地方公共団体の福祉担当窓口に連絡を入れましょう。
説明を聞いた後で融資を受けると決めたら、申込書に必要事項を入力して提出します。
提出したら審査が実施されるため、結果が出るまで待ちましょう。
審査結果が出たら、融資を受ける流れです。
自分が利用できる融資制度を知って、申し込みましょう。
公的融資制度の審査は利用条件に合うかが重要
公的融資制度の審査は、利用条件に合うかが重要です。
条件に合わない融資に申し込むと、借り入れできません。
生活福祉資金貸付制度では、利用できる世帯を低所得世帯や高齢者世帯に限定しています。
求職者支援資金融資制度を利用できるのは、失業保険を受け取れない人のみです。
生活困窮者向けの公的融資制度であっても、返済が難しい状態なら審査に通りません。
民間の金融機関から多額の借り入れをしている人や返済が滞っている人は、借り入れの整理をしなければ審査通過が難しいです。
返済の見通しが立たない人は、債務整理も検討しましょう。
債務整理の方法が分からないときは、法テラスで相談に乗ってもらえます。
法テラスとは国が設立した法的トラブル解決を目的とした機関です。
無料の法律相談も実施しているため、利用したい人は問い合わせましょう。
市役所や国から即日でお金を借りるのは難しい
市役所や国の公的融資制度では、即日の借り入れに対応できません。
例えば生活福祉資金貸付制度は、融資までに1ヶ月かかるケースもあります。
資金審査(広島県社会福祉協議会)により、資金の貸付の必要性、借入金額の妥当性、償還の見込み、自立の見込みを総合的に審査し、貸付の可否の判断をします。
なお、審査の都合上申し込みから貸付交付まで1ヶ月以上かかることもあります。(緊急小口資金は1週間程度かかります。)
出典:生活福祉資金貸付制度│権利擁護支援センター
緊急に融資を実施する緊急小口資金でも、融資までに1週間程度必要です。
生活福祉資金貸付制度で融資できるか判断する際は、民生委員による面談や生活安定を目的とした支援も実施されます。
総合的な判断を元に融資を決定する流れで、審査に時間をかけなければいけません。
すぐに借りられるわけではないため、お金がないときはできるだけ早く相談しましょう。