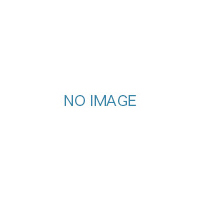東アジア共生会議2012レポート その1

大井 優子
東アジア共生会議2012 セッション1
12月15日、16日の2日間にわたり、仙台市の国際センターで東アジア共生会議2012が開催されました。この会議は、これまで文化庁が国際文化フォーラムとして開催していたものが、2011年度より東アジア諸国との共生についてよりフォーカスするようになったものです。東日本震災を受け、災害と共生について様々なお話がありましたが、一番感じたメッセージは、共感することが、理解や感動、行動につながる、すべてのはじまりであるということでした。それは一人ひとりの声や、アーティストが表現することで他者とよりわかちあえるようになることもあるし、それらすべてが文化であることのように思いました。
公式な記録は追って作成されますが、それぞれのセッションで印象に残った発言をご紹介します。
 ルーブル美術館クラウディア・フェラッツィ副館長
ルーブル美術館クラウディア・フェラッツィ副館長
<12月15日>
冒頭の奥山恵美子仙台市長の挨拶で、「市として震災対策をハードの面では進めていたが、文化の力を考えたことはなかった。今回、オーケストラの音がこんなにも人々を勇気づけるものだと実感し、復興の中での文化の位置づけについて考えていく必要がある。」といった趣旨の発言がありました。オーケストラとなると、コンサートホールに足を運ぶ一部の人しか聞く機会もないのかもしれませんが、仙台フィルは震災後、四重奏などの小編成で避難所や街中で200回を超えるコンサートを行ってきました。研鑽を積んだプロの演奏は、とても力強かったり、あたたかかったり、それぞれの心に響くものだったと思います。こうして生の音楽に身近にふれ、支えられる、あるいは癒されるといった時間は、非常時でなくても各地で広げていってほしいと思います。
ルーブル美術館のクラウディア・フェラッツィ副館長の基調講演では、これまで見せるだけだった美術館の使命が変わってきたことにふれ、「すべての人に開かれた美術館を目指している」と強調されていました。その例えに「毎日公演を行って市民にひらかれている劇場と同じように」といった表現をされていましたが、ヨーロッパではあたり前の劇場のイメージが、日本では事情が少し異なります。時間の芸術であり、1回限りの生の体験、キャパシティの制限というのは、動員にとってマイナス要素のようにも思えていましたが、いま求められる(提供したい)新鮮な企画を考えて広報活動を続けることができれば、逆に劇場の存在のPR効果も高まるという側面を感じました。また、ルーブル美術館の年間入場者の約半数は30歳以下、日本の文化芸術機関の広報や発信についてもこうした取り組みに学ぶことがあると感じました。
東日本大震災の被害があまりにも甚大だったこともあり、日本では、文化芸術に携わる人も、美術品を守ったり、音楽などを提供することに躊躇してしまうような時期もありました。そんな中、ルーブル美術館が、東北3県で所蔵品の巡回展の実施にふみきったのは、「危機の後、美しいものを求める傾向があり、経済状況が厳しいときほど関心が高まる」といった、これまでのリサーチがあったからだと述べていました。文化芸術の力や社会における役割について、日頃からリサーチされて、組織の中での共通理解ができているからこそ、素早く行動に移すことができのだと思います。
 和合亮一氏(詩人)
和合亮一氏(詩人)
福島に生きる詩人の和合亮一さんは、被災した避難所生活で「人はパンのみに生きる」じゃないか、と思ったこともあったそうです。しかし、言葉を描き続けることで目覚め、自分を取り戻すことができた。書くことで、守るべきものがあるから生きられると思い「人はパンのみに生きるにあらず」を実感したそうです。原発事故による放射能汚染を受けた福島の今の現状は、子どもたちが大人になっても変わらない。言わなければ、その先は言えないし、今の憤りを言葉に紡ぎ形にしていく、子どもに伝えることを繰り返していくしかありません。人が集まることが守ることのはじまりであり、震災をどうデザインしていくかが、芸術のはじまりだと考えるに至った。文化について話をすることが、人生そのものであり、人間はアーティストととらえるべきではないか、といった発言をされていました。アートは、人間の創造性の発露であり、それは誰もが日常的な営みの中で行っていることだとも思います。表現をより高めた先が一般的に想像される「芸術(High Art)」となるのかもしれませんが、まずは言葉で伝え、イメージを共有するという日常的な営みは、社会を形成する上で大切な要素となっているように感じました。
音楽の力による復興センター東北代表理事の大澤隆夫さんは、過去のピュリッツァー賞受賞者の言葉を引いて、災害が起きると「これまでになかった大きな回路ができる。そして、それはまた閉じる。」ということを提示されました。仙台フィルは震災により閉校となる学校の校歌をCD化し、何をどういう風に残すべきか、仙台にホールをつくり経済振興、演奏を届ける、自分たちの演奏で立ち上がることに向かっています。ただ、いま様々な形で外部との連携がもたれてきていますが、いつしか閉じてしまうのではなく、閉じないで通じていてほしいという願いは、みなさんもたれていることだと思います。それを可能にするのは、生きたネットワークが保たれることでしょうか。こうした国際的なシンポジウムで認識されたことで、国もぜひそういった視点を常にもって、海外との交流事業を発展させていってほしいです。
建築家の妹島和世さんは、ご自身も復興計画に携わり住民の方と接する中で、地域の人の求めることが変わってきていることをお話しされていました。当初は現地の方も早く住む場所をつくらないと、と道路や区分けといったハードのプランを進めていたのが、今は、次のステップのビジョンを描いてほしいと言われるそうです。新しい街ができるまで待ちきれず、街を出ていく人が増えてきているため、街の人が被災した土地から出ていかないで、ここでがんばろうと思えるビジョンがほしいと言われるそうです。他の海外のアーティストのお話からも、このセッションでは、想いを言葉にすること、「美しい」を共有することが守ることにつながるといったエピソードが語られましたが、被災地に住む方々の間でもまさに未来のイメージを描き、共有することが必要とされているのだと思います。
写真提供:文化庁
 ご覧のページは、これまでのコンソーシアムのホームページを活用し、コンソーシアムの活動記録や資料等をアーカイブ化したものになります。
ご覧のページは、これまでのコンソーシアムのホームページを活用し、コンソーシアムの活動記録や資料等をアーカイブ化したものになります。